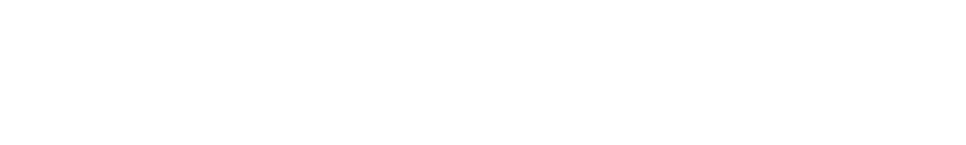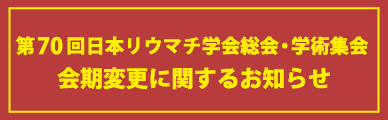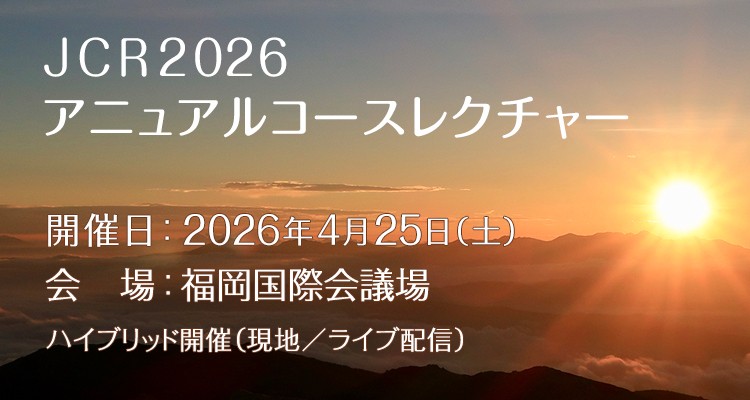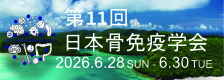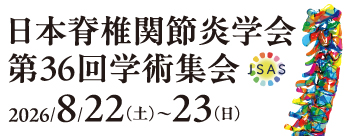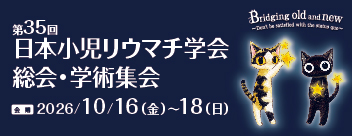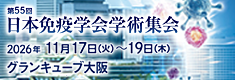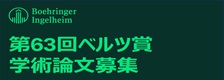会長挨拶

第70回日本リウマチ学会総会・学術集会
会長 渥美 達也
北海道大学大学院医学研究科 免疫・代謝内科学分野 教授
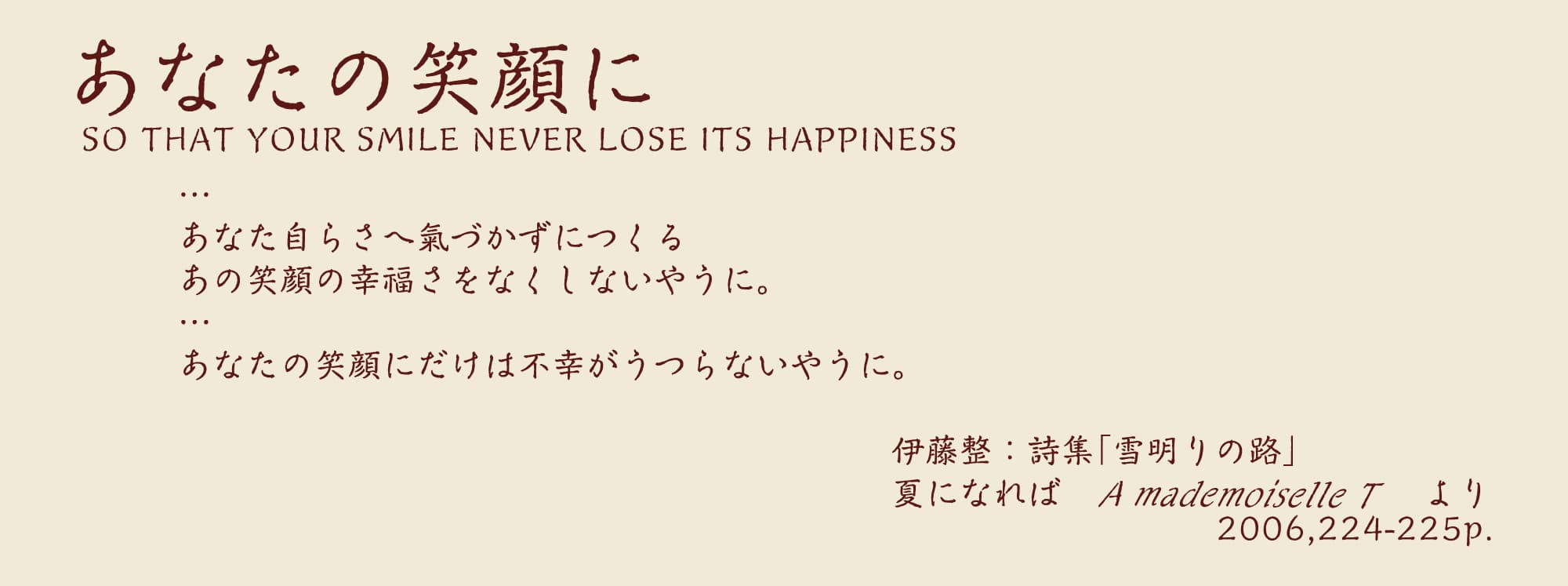
詩人・小説家・翻訳家の伊藤整(1905-1969)は、学生時代を北海道・小樽で過ごしました。塩谷(しおや)村から旧制・小樽中学校(現・小樽潮陵高校)、小樽高等商業学校(現・小樽商科大学)へは毎日汽車で通学し、学生の時期に日々経験したこと、感じたことを多くの詩に残しています。伊藤が自費出版した詩集「雪明りの路」は、大正時代Teenagerであった伊藤の感性あふれる抒情詩集です。
伊藤は、自宅のあった塩谷にほど近い漁村である忍路(おしょろ)に住む漁師の娘に恋心をいだきます。冬や雪の情景が多いこの詩集のなかで、夏の日に書いた珠玉の作として登場するのが、「夏になれば」です。伊藤は緑あふれる夏の日の小樽の街で、たまたますれ違ったその娘にほほえみがちに挨拶され、その笑顔に何か強い思いを感じます。そして、自分の気持ちはうちあけられないけれど、彼女がいつか誰かの妻となり母となっても彼女の笑顔から幸福が消えないことを自分は祈ろうと、心のなかで誓うのです。
第70回日本リウマチ学会学術集会は、新緑の福岡で開催されます。70年を振り返ると、私がいうまでもなくリウマチ性疾患の治療は飛躍的に進歩しました。全身性エリテマトーデス(SLE)は日本リウマチ学会が創設された70年前は3年生きられる確率が60%ほどでしたが、グルココルチコイドの大量投与が可能になって、生命を救うことができる疾患になりました。一方で、グルココルチコイドは代謝に大きな影響を与えるため、その長期投与に伴う合併症のため患者さんは制限の大きな生活を余儀なくされました。しかし、約35年前にはシクロフォスファミド間歇静注療法、15年程前にはミコフェノール酸モフェチル、8年前には最初の生物学的製剤、4年前には別の機序をもつ生物学的製剤、そして2年前には腎炎に対して高い効果をもつ新規カルシニュリン阻害薬と、時間がすすむにつれて有効な薬剤が承認され使われるようになりました。治療薬や治療プロトコールの進歩によって、副作用の強いグルココルチコイドへの依存度が次第に減少してきました。本邦のSLE診療ガイドラインには、SLEの治療目標はSLEでないひとと何らかわらない社会生活が送れる状態、すなわち「社会的寛解」を維持すること、と記載されました。この高い治療目標が現実のものとなっています。関節リウマチの治療の進歩はさらに加速度的で、70年前は高度の関節破壊のために生活や生命が損なわれる患者さんが多くいましたが、40年前にはメトトレキサートが米国で承認され、この薬剤を使用した患者さんは関節炎のコントロール状態が大変よくなりました。そして20年前に登場した生物学的製剤・抗サイトカイン療法によって、私たちは関節予後や治療目標さえも完全に変えることに成功し、関節リウマチ治療のパラダイムシフトの到来とよばれました。さらに10年前から分子標的合成抗リウマチ薬によって生物学的製剤に勝るとも劣らない効果が経口薬でも可能となり、患者さんの状態や生活スタイルにあわせての治療の選択肢が増えました。70年の時間をあらためてさかのぼると、これらの治療の進歩は、文字通り指数関数的であるといえるでしょう。
治療の進歩によってもたらされるのは、患者さんの笑顔です。患者さんに発症前の笑顔がもどれば、医師・医療スタッフそして膠原病・リウマチ診療にかかわる人すべてにも笑顔が生まれます。しかし、今ある治療薬ではまだ寛解には至らない患者さんがいます。寛解に至っても再燃してしまうこともありますし、長期の治療に伴う合併症により生活レベルが損なわれることもあります。これからの私たちに必要なことのひとつめは、膠原病・リウマチ性疾患の病因や病態研究をいっそうすすめて高い寛解率をもたらすあらたな治療薬を開発すること、ふたつめは、合併症なく治療効果が長く続いて生活レベルをずっと維持できるような治療プロトコールおよび外科治療を開発して確立することです。私たちは70年のリウマチ学の進歩に驕ることなく、いっそうの努力を継続する必要があります。患者さんの笑顔から、リウマチ・膠原病の診療に関わる医療者の笑顔から、ずっと幸福さが失われないように。